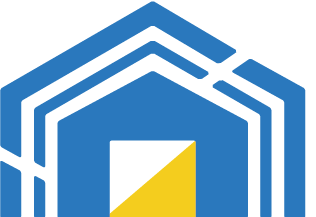本コラムでは、相続人に認知症などの判断能力のない方がいる場合に、遺産分割協議をどのように進めるべきかを解説します。
高齢化が進む中、「相続人のひとりが認知症になっていて話し合いができない」といったご相談が増えています。遺産分割協議は全相続人の同意がなければ成立しないため、対応を誤ると手続きが止まってしまうことも。こうした状況に備え、正しい知識と手続きを知っておくことが重要です。
目次
◼︎認知症の相続人がいると遺産分割協議はできない?
遺産分割協議は、すべての相続人が「意思能力」をもって合意する必要があるため、認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合、そのままでは協議を進めることができません。
仮にその相続人を除いて協議を行ったとしても、その協議は無効とされる可能性が高く、後にトラブルや裁判に発展することもあります。
したがって、まずは「判断能力があるかどうか」を明確にすることが第一歩です。
◼︎家庭裁判所への申し立てが必要になるケース
認知症で遺産分割協議に参加できない場合には、家庭裁判所に「成年後見制度」の申し立てを行い、後見人を選任してもらう必要があります。
・成年後見制度とは?
本人の代わりに法律行為を行うことができる代理人(成年後見人)を裁判所が選任する制度です。後見人は、相続人本人の利益を守りながら、遺産分割協議に参加します。
・申立人は誰?
他の相続人、親族、または市区町村長などが申し立て可能です。
・選ばれる後見人は誰?
家族が選ばれることもありますが、利益相反などの懸念がある場合は弁護士や司法書士など第三者が選ばれることもあります。

◼︎遺産分割協議における注意点
後見人が就任すれば遺産分割協議を進めることは可能ですが、以下の点には注意が必要です。
・後見人が本人の利益を損なう内容には同意できない
たとえば、不動産を他の相続人がすべて取得する代わりに金銭で清算するといった配分が不公平な場合、協議は進まないことがあります。
・後見人と他の相続人が同一人物の場合、特別代理人の選任が必要
利益相反関係にある場合、改めて「特別代理人」の選任が必要です。
・時間と費用がかかる
成年後見制度の申し立てには通常1〜3か月程度かかり、医師の診断書や手数料も必要になります。
◼︎まとめ
相続人が認知症の場合、遺産分割協議は「そのままでは進められない」というのが基本です。成年後見人の選任を通じて適切に代理人を立て、法的に有効な手続きを踏むことが必要です。
こうしたケースは、法的・感情的な配慮が必要な場面が多く、専門家のアドバイスが欠かせません。
複雑な状況に悩んでいる方は、早めに信頼できる司法書士や弁護士へ相談し、円満な相続を実現しましょう。
※本記事は一般的な情報に基づいて作成しています。具体的なご事情によって必要な手続きや税額は異なりますので、詳細については専門家にご相談ください。
相続に関するお悩みがある方は、大阪相続相談センターまでお気軽にご相談ください。円満な相続の実現に向けて、誠実にサポートいたします。