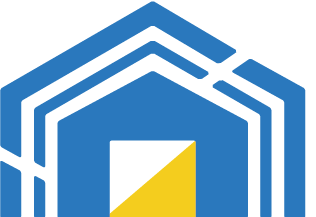本コラムでは、相続した不動産を売却する際に発生する税金や確定申告のポイントについて解説します。
親から土地や建物を相続したけれど、自分で住む予定もないし管理も大変…そんなときに「売却を考えたい」と思う方は多いものです。
しかし、相続した不動産を売却するときには、税金の申告や手続きのタイミングに注意が必要です。知らずに進めると、後になって思わぬ税負担が発生する可能性もあります。
◼︎売却前に知っておきたい「相続登記」と名義変更
相続した不動産を売却するには、まずその不動産の「名義(登記)」を自分に変更する必要があります。これを「相続登記」といいます。
2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、正当な理由がなく3年以内に登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
売却活動を始める前に、必ず名義変更を済ませましょう。
◼︎相続不動産の売却にかかる税金とは?
不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合には、「譲渡所得税」という税金がかかります。これは所得税・住民税・復興特別所得税を合計したもので、以下のように計算されます。
・譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
この中でポイントになるのが「取得費」です。相続の場合、被相続人が購入したときの金額を引き継ぐことになりますが、取得費が不明な場合には概算取得費(売却額の5%)で計算されることもあります。
※取得費が小さいと譲渡所得が大きくなり、結果的に税金が増える可能性があります。

◼︎「3,000万円の特別控除」が使える場合もある
自宅として住んでいた不動産を相続し、一定の条件を満たす場合には、「被相続人の居住用財産の3,000万円控除」という特例が適用され、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。
ただしこの制度は、以下のような条件付きです。
・相続開始直前まで被相続人が住んでいたこと
・相続から一定期間内に売却していること
・空き家のまま売却されたこと など
利用には細かな要件があるため、事前に税理士などに確認することが大切です。
確定申告は必須!期限にも注意
相続した不動産を売却して利益が出た場合は、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。
申告を忘れると、延滞税や加算税などのペナルティが発生するおそれもあります。
また、譲渡損失が出た場合でも申告することで、他の所得と損益通算したり、翌年以降に繰り越したりできる可能性があります。
◼︎まとめ
不動産の相続と売却は、登記や税金、確定申告など複雑な手続きが伴います。
「相続登記をして終わり」ではなく、売却によって新たな税負担や申告義務が生じることを理解しておくことが大切です。
不動産の売却を検討している場合は、早めに専門家に相談し、特例の活用や税務リスクの最小化を図りましょう。
※本記事は一般的な情報に基づいて作成しています。具体的なご事情によって必要な手続きや税額は異なりますので、詳細については専門家にご相談ください。
相続に関するお悩みがある方は、大阪相続相談センターまでお気軽にご相談ください。円満な相続の実現に向けて、誠実にサポートいたします。