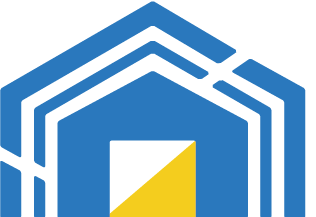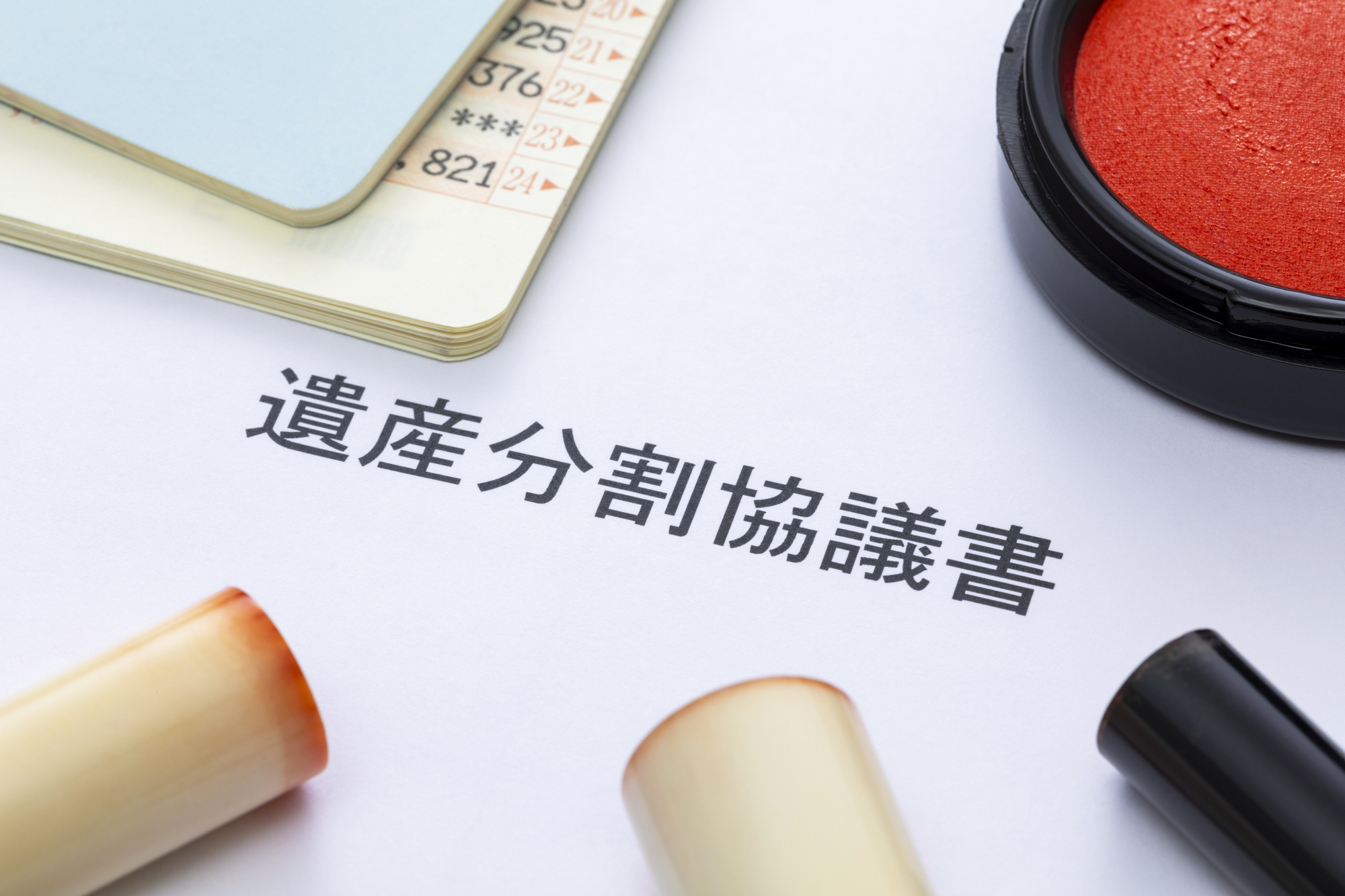
本コラムでは、遺産分割協議の基本的な仕組みと、話し合いがまとまらない場合の対処法について解説します。
相続が発生したあと、避けて通れないのが「誰が何を相続するのか」という話し合いです。特に不動産や預貯金などが複数人で共有される場合、遺産の分け方を巡って意見が対立するケースも少なくありません。
トラブルを防ぐためにも、遺産分割協議の進め方と、万一合意に至らないときの対応をしっかり押さえておきましょう。
目次
◼︎遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、法定相続人全員が参加し、相続財産の分け方を話し合う手続きです。
遺言書がない場合、相続財産は原則として法定相続分に従って分けられますが、実際の生活状況や資産の性質を考慮して話し合いで調整することが一般的です。
協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・押印することで法的効力が発生します。この書面は、不動産の相続登記や預金の名義変更などに必要となります。
◼︎協議がまとまらないときに起こる問題
遺産分割協議は、法定相続人全員の同意がないと成立しません。 つまり、一人でも納得しなければ協議は無効となり、財産の名義変更や分配が進められない状態が続きます。特に以下のようなケースで揉めやすくなります。
・相続人の人数が多い
・特定の相続人が財産の多くを取得していた
・生前贈与を受けた人と他の相続人の間で不公平感がある
・遺産の大部分が不動産など分けづらい資産である
このような場合、感情的な対立や不信感が積もり、家庭内の関係に深刻な影響を及ぼすこともあります。

◼︎話し合いがまとまらないときの対処法
協議が難航したときには、以下のような手段で解決を図ることが可能です。
1. 専門家への相談(税理士・弁護士・司法書士)
中立的な第三者である専門家を間に入れることで、感情的な衝突を避け、事実や法律に基づいた冷静な話し合いが進めやすくなります。
2. 家庭裁判所への「遺産分割調停」
協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
調停委員を交えて話し合いを行い、合意を目指します。調停でも解決しない場合は、審判(裁判所による判断)に進むことになります。
3. 相続放棄や部分協議も視野に
特定の財産についてだけ先に協議を進めたり、他の相続人が放棄を検討したりすることで、全体の話し合いが進みやすくなる場合もあります。
◼︎まとめ
遺産分割協議は、相続手続きの中でも最も重要かつ繊細なプロセスです。話し合いが円満に進めば相続もスムーズに終わりますが、対立が生じると手続きが長期化し、家族関係にも亀裂が生じかねません。
だからこそ、早めに専門家の力を借りて客観的な視点で整理することが、後悔しない相続の第一歩です。
※本記事は一般的な情報に基づいて作成しています。具体的なご事情によって必要な手続きや税額は異なりますので、詳細については専門家にご相談ください。
相続に関するお悩みがある方は、大阪相続相談センターまでお気軽にご相談ください。円満な相続の実現に向けて、誠実にサポートいたします。