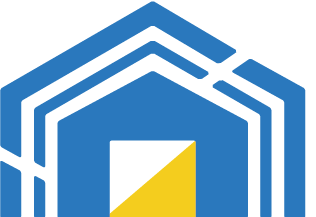「不動産は子どもたちで仲良く共有させればいい」と思っていませんか?
共有名義には確かにメリットもありますが、一方で管理や処分をめぐって対立が生じやすく、将来的に売却や相続の手続きが複雑になる可能性もあります。
本コラムでは、不動産を共有名義で相続した場合の仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく整理し、トラブルを防ぐためのポイントを解説します。

目次
◼︎不動産の「共有名義」とは?
不動産の共有名義とは、ひとつの物件を複数の人が共同で所有している状態を指します。
たとえば、親が亡くなった際にその自宅を兄弟姉妹3人で相続し、登記簿上の名義を3人に分けると「共有名義」となります。
所有者それぞれが持分を持ち、勝手に売却や賃貸などはできないという制限がかかります。
遺言書がない・内容が曖昧
遺言書がない場合、法定相続分に従って分割を協議することになりますが、意見の食い違いや感情のもつれが生じやすくなります。
また、遺言書があっても内容が不明確だと、かえって争いの種になることも。
特定の相続人に財産が偏っている
生前贈与を多く受けた相続人がいる、または遺言で一部の人に財産が集中している場合、「不公平だ」と感じた他の相続人との間で対立が起こることがあります。
共有名義の不動産がある
複数の相続人で不動産を共有すると、「売る・貸す・住む」などの意思決定に合意が必要になり、意見が割れる原因になります。
相続人同士の関係が良くない
兄弟姉妹間の関係がもともと悪かったり、疎遠であったりすると、コミュニケーション不足から不信感や対立に発展するケースも。
◼︎共有名義のメリット
遺産分割協議がまとまりやすい
相続人全員が納得すれば、「とりあえず共有にしておこう」という形で早期に協議がまとまるケースがあります。
特定の相続人に偏らない
不動産が1つしかない場合でも、複数人で所有することで「平等に受け取った」という印象を与えやすくなります。
すぐに売却しなくてもよい
現金化を急がず、「とりあえず持っておく」選択肢がとれる点も一部にはメリットといえます。

◼︎共有名義のリスク・デメリット
意思決定が難しい
不動産の売却やリフォーム、賃貸などの重要な決定には、共有者全員の合意が必要です。
1人でも反対すると進められないため、スムーズな運用が難しくなることがあります。
相続人の数が増えるとさらに複雑に
共有者のうち1人が亡くなると、その持分がさらに次世代に相続され、名義が細分化していきます。
結果として「共有者が10人以上」「連絡が取れない人がいる」といったケースも起こりえます。
持分の売却・処分が制限される
持分のみの売却は買い手がつきにくく、売却価格も下がりがちです。また、共有者以外に持分を譲渡すると、新たな第三者との関係性が発生し、さらなる管理の煩雑化を招きます。
◼︎トラブルを防ぐための対策
遺言書で相続方法を明確にしておく
生前に「誰にどの不動産を相続させるか」を遺言で決めておくことで、共有を避けることが可能です。
代償分割や換価分割の検討
現金や他の資産を調整に使い、不動産を特定の相続人に集中させる「代償分割」や、物件を売却して現金で分ける「換価分割」も有効な手段です。
す。
共有になってしまった場合は早めに話し合いを
共有名義のまま放置するのではなく、将来に備えて売却や持分の集約について、早めに家族で話し合うことが大切です。
◼︎不動産の「共有名義」とは?
不動産の共有名義相続は、初期の協議をスムーズに進める手段にはなりますが、長期的に見るとトラブルの温床にもなりかねません。
将来の分割・処分・管理のことまで見据えたうえで、「本当に共有で良いのか?」をしっかり検討することが重要です。
不動産を相続予定の方や、すでに共有名義になっている方は、早めに専門家に相談し、最善の方法を見つけておくことをおすすめします。
※本記事は一般的な内容に基づいて作成しています。具体的な事情により必要な手続きは異なるため、詳細は専門家にご相談ください。
相続や遺言に関するご相談は、大阪相続相談センターまでお気軽にどうぞ。
専門スタッフが誠実にサポートいたします。