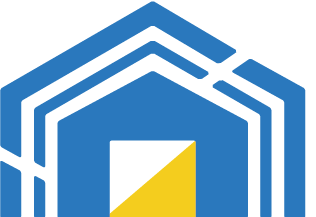本コラムでは、見落とされがちな「二次相続」のリスクとその対策方法について解説します。
相続対策というと、親が亡くなった直後の「一次相続」に意識が集中しがちですが、実はその後に訪れる「二次相続」にこそ注意が必要です。
配偶者が財産を多く相続した場合、その後に残された家族に重い相続税がかかるケースもあるため、早めの対策が大切です。
◼︎そもそも二次相続とは?
相続は通常、親のどちらかが亡くなった際に一度(一次相続)、もう一方の親が亡くなったときにもう一度(二次相続)発生します。
たとえば父が亡くなり、母と子ども2人が相続人だった場合、父の相続が一次相続。母が亡くなった際に、子ども2人で財産を分けるのが二次相続です。
◼︎見落とされがちな「二次相続の落とし穴」
一次相続では、配偶者の税額軽減制度により、配偶者が取得する財産には相続税がほとんどかからないことがあります。
これに安心して財産の多くを配偶者に集中させてしまうと、次の「二次相続」で相続税が一気にかかる可能性があるのです。
さらに二次相続では、法定相続人の数が減るため、基礎控除額も小さくなります。
例:一次相続時
法定相続人:配偶者+子2人 → 基礎控除 3,000万円+600万円×3=4,800万円
例:二次相続時
法定相続人:子2人のみ → 基礎控除 3,000万円+600万円×2=4,200万円
このように、相続税の対象となる金額が増えやすくなるのが、二次相続のリスクです。

◼︎二次相続対策でできること
1. 一次相続時に分散相続を検討する
一次相続で配偶者にすべての財産を集中させるのではなく、子どもにも一部相続させておくことで、二次相続時の税負担を軽減できます。節税だけでなく、財産の分散によるトラブル回避にもつながります。
2. 遺言書の活用
将来の分配方針や割合を明確にすることで、相続人同士の争いや誤解を防ぐことができます。「配偶者に多めに残す」「子には特定の資産を残す」など、具体的な意図を残しておくことが重要です。
3. 生前贈与の活用
年間110万円までの非課税贈与を活用すれば、少しずつ子どもへ財産を移転できます。また、相続時精算課税制度を使えば、贈与時にまとめて申告し、相続時に調整する形も可能です。
◼︎まとめ
二次相続は、タイミング的に油断しやすく、結果的に大きな税負担を招くリスクがあります。
だからこそ、一次相続の段階から「その次」を見据えた対策を講じておくことが大切です。
相続は家族の未来に関わる大切なテーマ。節税と円満な承継を両立するためにも、ぜひ早めに専門家にご相談ください。
※本記事は一般的な情報に基づいて作成しています。具体的なご事情によって必要な手続きや税額は異なりますので、詳細については専門家にご相談ください。
相続対策に不安のある方は、ぜひ大阪相続相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
経験豊富なスタッフが、丁寧にサポートいたします。